施設概要
| 名称 | さくらキッズガーデン |
|---|---|
| 所在地 | 〒154-0014 東京都世田谷区新町3-21-3 |
| 理事長 | 芳村 起代子 |
| 園長 | 千野 郁子 |
| 敷地面積 | 819.78㎡ |
| 建築面積 | 315.57㎡ |
| 述床面積 | 653.82㎡ |
| 園舎構造 | 鉄筋コンクリート造三階建/地下1階 |
| TEL/FAX | 03-3428-6474(代) / 03-5451-3321 |
東急田園都市線桜新町駅北口徒歩2分
送迎バスは用意していません。
通園は親とこのコミュニケーションの為の大切な時間と考えています。
また、この送迎の時間を利用して、園内での子どもの生活を把握したり、担任とのコミュニケーションを図ることもねらいとしています。
施設紹介
子どもたちの長期滞在をふまえて、楽しく、からだに優しい安全な園舎を目指して設計されました。園舎内は明るく、あそびの空間もさまざまな工夫がこらされています。
また、建築素材も充分に吟味し、天然のムク材、コルクタイル、 植物性リノリューム、さらには身体に安全な塗料を使用。アレルギーやアトピーの原因となる要素を排除し、健康に気づかった園舎となっています。

最寄り駅から徒歩2分に位置する当園は、地下1階から地上3階建ての園舎です。
園庭には様々な年齢の子どもたちが遊べる遊具が設置されています。

地下1階ホール
ここでは各式典や生活発表会などが行われます。

2階につながる階段部。黒い板塗部分は地下ホールの屋根を利用しています。
滑り台として子どもたちのお気に入りの遊び場です。

玄関ホール

保育室の床はすべて唐松のフローリングを使用し、植物性のワックスをかけています。

人の顔のように見える保育室の扉。
目の部分は子ども用、眉の部分は大人用ののぞき窓です。
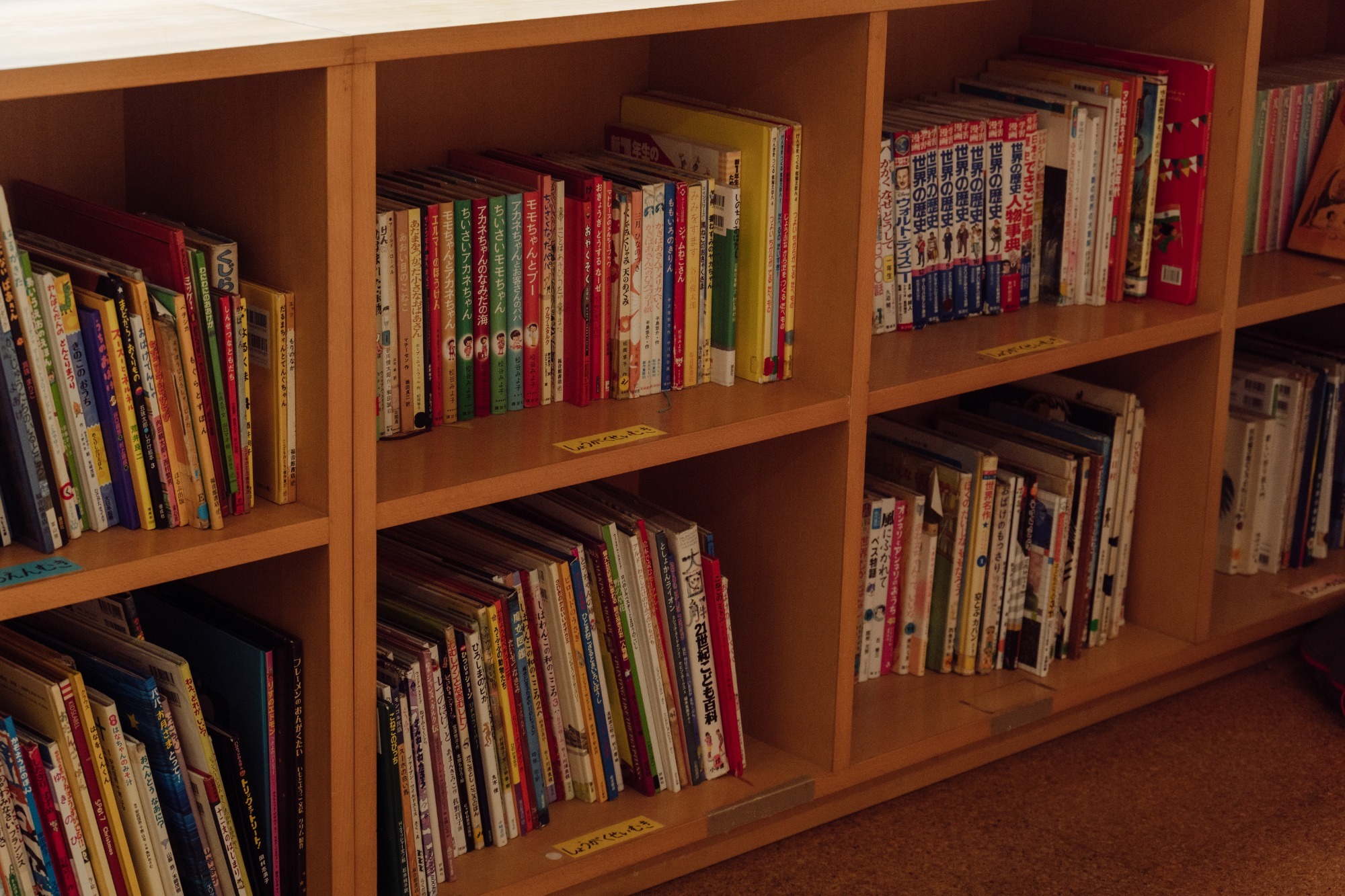
図書コーナー
幼稚園には様々な年齢向けの絵本がたくさんあります。

3階保育室

保育室の窓には指つめ防止機能つきの器具を使用しています。
ナーサリーさくらキッズ
保育対象

0歳~就園前のお子様
保育時間

月~土曜日:午前7時30分~午後7時まで
※但し午後6時から7時までは別途延長料金がかかります
昼食

全員完全給食です。毎月事前に献立を皆さんにお知らせしています。
メニューは栄養士により栄養バランスを配慮しながら献立を製作しています。おやつを含めて全て手作りです。
休園日

12月29日から1月3日まで
未就園児クラス
からだを動かしたり、歌ったり、リズムにのって英語を話したり、試行錯誤したりと盛りだくさんの内容に毎日ワクワク、ドキドキ!集団生活を通していろいろな経験をしていきます。
お母様もすてきなお友だちをつくって皆でいっしょに楽しく子育てをしていきましょう。
保育対象
幼稚園に入園する1年前のお子様
保育時間
月~金曜日:午前9時~午後13時
はじめは11時頃降園からスタートし、徐々に降園時間をのばしていきます。
コース
週2・週3コース
6月頃から全員週5日コースになります。
カリキュラム
- リトミック
- 英語
- 体操
- SI遊び
さくら幼稚園
園の歴史
昭和23年、さくら幼稚園は初代園長・小林宗作によって創立されました。
小林宗作は現在の東京芸術大学を卒業後、成蹊小学校の音楽教師となり、ここで成蹊の 創立者・中村春二先生の「自由な教育、子どもの個性尊重に徹する教育方針」に大きな影響を受けました。
その後、音楽教育、児童教育を学ぶ為に渡欧、パリのダルクローズ音楽学院では、ダルクローズ氏から直接「リトミック」を学んでいます。
帰国後、小原国芳氏とともに成城幼稚園を創立。さらに、小原氏が玉川学園、小林はトモエ 学園を創立するなど、日本の児童教育に大きな足跡を残すとともに、リトミックの国内普及に努めました。
「子どもを先生の計画にはめるな。自然の中に遊ばせておきなさい。先生の計画より子ども の夢のほうがずっと大きい」
小林の教育理念に基づき、戦後の荒廃した時代の中、未来を たくす子どもたちを育てるためにさくら幼稚園が誕生しました。
以来半世紀、この小林の理念は、新生さくらキッズガーデンの中にも脈々と活き続けています。
保育内容
さくら幼稚園ではさくらキッズガーデンの教育理念に従い保育内容を充実させています。

知能を育てる教育
S・I あそび
幼児期は知能がほぼ完成するとき。知能を育てる為には「教える」のではなく、「気づかせる」ことが大切です。正しい知能発達理論に基づき、適切な知能刺激を与える「S・I (エスアイ)あそび」を実施し、子どもたちの知能向上を目指します。

豊な感性を育てる
リトミック
幼児期に最も成長する音楽的感覚を養うことを目的とする教育が「リトミック」です。音楽反応あそびを通じて、リズムを体で覚え、音楽を自然に楽しく体験します。そして音楽的感覚を養うことにより「集中力」「判断力」「反射力」「想像力」「表現力」を深めることに成果をあげています。

異文化・異言語理解
英語教育
異文化を体験し、国際感覚を身につけることは、これからの国際社会においては不可欠な物です。専門教師の手法により、子どもたちを飽きさせない遊びの要素を取り入れた「英語教育」を実施。生きた英会話を身につけていくことで、異文化吸収の為の基礎を作ります。

健康な体を育てる
体育あそび
かたよりのない身体運動や運動機能の発達のために、精選したカリキュラムに基づいた「体育遊び」を実施しています。さまざまな運動遊具の導入や、体育担当の男性教師よるきびきびとしたダイナミックな実践指導により、子どもたちは楽しみながらからだを動かす喜びを覚えていきます。
保育対象
3歳~就学前のお子様
保育時間
月・火・木・金曜日:午前9時から午後2時まで
水曜日:午前9時から午後0時30分まで
昼食
幼稚園は基本的に手作り弁当をすすめていますが、状況に応じて給食を利用することも可能です。
※希望者は当日の朝有料でご注文いただくことができます
休館日
学校法人創立記念日:5月2日
夏期期間:山の日含むお盆期(事前に年間予定表でお知らせします)
年末年始:12/27~1/4
時間外保育について
ピッキークラブ
諸事情によって家庭で保育できない在園児を対象に、時間外保育を行っています。
月~金曜日:
- 午前7時30分から9時まで
- 通常保育終了後から午後7時まで
※但し午後6時30分から午後7時までは別途延長料金かかります。
長期休業期間:
- 午前7時30分から午後7時まで
※但し午後6時30分から午後7時までは別途延長料金かかります。
もあくらぶ
急な用事ができて迎えが間に合わない時など、当日朝のお申込みにより延長保育を行ないます。(有料)
月~金曜日:
- 通常保育終了後から午後5時まで
- 長期休暇中、及び行事前などはお預かり出来ません。(事前に年間スケジュールをお知らせします)
さくら学童クラブ
育成対象:小学校1~3年

(親が就労、介護などで児童育成に支障があると思われる家庭)
★小学校4年生から6年生までは「キッズサポート」が対象となります。ご相談ください。
育成時間

月~金曜日:
学校終了後から午後7時まで
(※但し午後5時から7時までは別途延長料金がかかります。)
長期休業期間(春・夏・冬休み):
午前7時30分から午後7時
(※但し午前7時30分から午前9時、午後5時から7時までは別途延長料金がかかります。)
休園日

12月27日~1月4日まで
クラブにおける子どもの生活
■午後1時~2時:下校~入所
■3時~3時30分:宿題・勉強始め
■3時50分:おやつ/工作などの自由遊び
■4時40分:掃除
■5時00分:退所
課外活動
新体操教室

【対象】
3・4・5歳、小学生
【曜日】
金曜日
【時間】
3・4・5歳/午後2時15分~
小学生/午後3時~
体操教室

【対象】
4・5歳、小学生
【曜日】
木曜日(地下ホール)
【時間】
年中/午後2時5分〜午後3時5分
年長/午後3時10分〜午後4時10分
小学生/午後4時15分〜17時15分
※指導 バディスポーツクラブ
英語教室

【対象】
3・4・5歳、小学生
【曜日】
金曜日
【時間】
3・4・5歳/午後2時15分~
小学生/午後3時~
さくら幼稚園こぐまコスモス教室




【対象】 年中、年長こぐま会
サクラス




【知能育成】コース:幼小一貫知育エデュケーション 【sucurus】
●サクラスとはなにか
sucurus(サクラス)とは、生きた学力を育成するために考案されたプラウダスのオリジナル知育教育です。幼稚園年長・小学1年生・小学2年生の3年間を「幼少一貫」として、試行錯誤と体験を通じて知的好奇心という「学力の種」をまいて発芽させるまでの一貫カリキュラムです。
【中学受験】コース:小3~小6対象
高校受験/中高一貫校補修/大学受験も、行っています。ご相談下さい。

